こんにちは。
「公文、もうやめたい」
そう言ったのは、小学1年の下の子。
まだ通い始めてたった1ケ月
「せっかく通わせたのに、こんなに早く辞めていいの…?」
そんな葛藤を抱えながら、私はしばらく悩み続けました。
私が、公文を早く辞める決断をした理由と、辞めてみて気づいた「本当の学び」について書いてみます。
※我が子の場合です。
公文が合わなかった一番の理由は「性格のタイプ」

公文は、「コツコツ型」「自分で進められる子」には向いています。
でも、うちの子はまさにその逆。
間違えるのが怖くて、1問に時間をかけすぎるタイプでした。
どんどん進めるより、じっくり考えたい子。
最初は私も「慣れれば大丈夫」と思っていましたが、
プリントを見るだけで顔が曇るようになってしまって…。
公文が合わなかった2番の理由は「教室の先生との相性」

そして、一緒に始めた上の子の一言で辞める決意をしました。
「先生が怖い」
体験の時、「先生が怖い」と言っていましたが、
まだ初回だし、これから慣れてくれればいいかなぁと安易に思っていました。
しかし、上の子も一緒に通っているのですが
先日、上の子が「また〇〇(下の子)先生に怒られてたよ」
と。
「そうなんだ」
「どんな感じで?」
「ちゃんと下のところを持たなきゃだめでしょ!!」
「もっと強く書いて!!」と怒鳴っていた」
と、上の子が私に教えてくれました。
「え!!そんな言い方なの?」
「うん」「私も見てて怖くなった」
「・・・・」
それじゃぁ行くのも嫌になるな。。。
公文から帰宅する時も、下の子は「行きたくない」と言う。
上の子が一緒で良かったです。
なぜなら詳しくどんな感じで怒られてたのかわかったから。
ネットのサイトでは「楽しく・・・」とか書いてあったのに・・。
そんな強い言い方していたなんて・・・。
マル付をする先生は優しいけど、〇〇(下の子)に教えている先生(教室の一番偉い中心的な人)が、怖いそう。
下の子は早産まれて、まだまだ長い時間数字や文字を書くのは不得意です。
なので、先生からしたら、イライラしてしまったのかもしれません。
下の子は苦痛になってきたところで、夫にプリントの量を見せたら、
「確かに今の〇〇にとっては、この量は多いかもね」と。
そして、ふと気づいたんです。
「勉強を嫌いにさせてまで続ける意味はない」と。
このまま続けていたら、計算やひらがなが嫌いになりそうな気がしました。
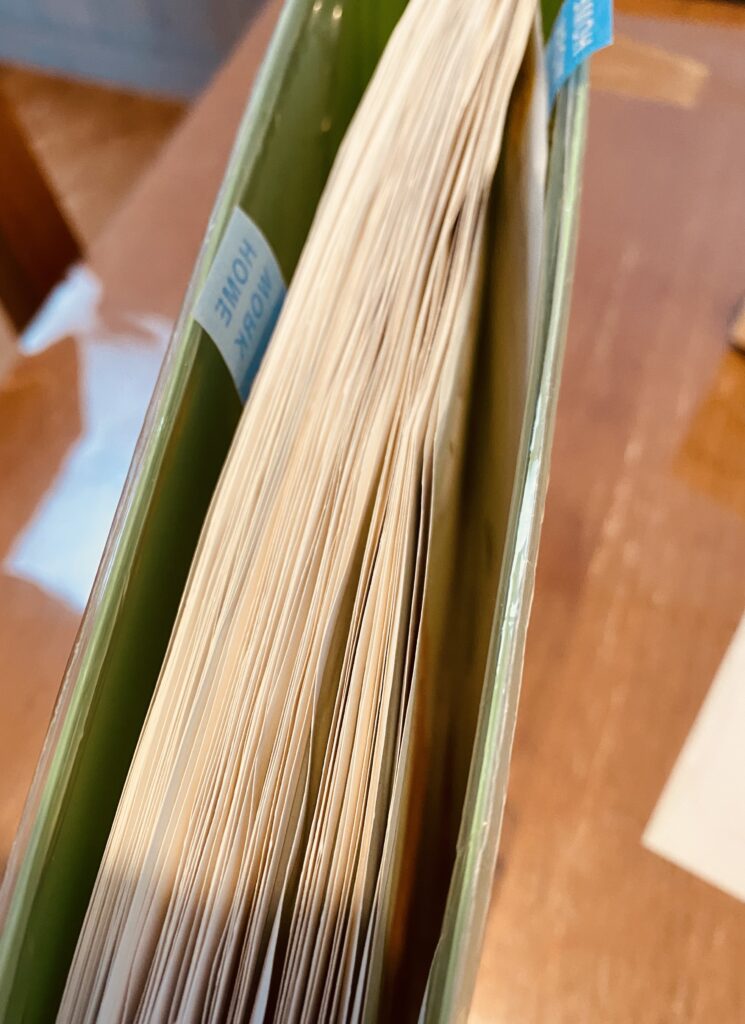
辞めたあとの“罪悪感”と、その先に見えたもの
正直、公文を辞めた直後は不安でいっぱいでした。
「みんな続けてるのに」「うちだけ遅れてしまうかも」
SNSでも「続けてよかった」という声ばかり見えて、
少し落ち込みました。
でも、辞めて数ヶ月。
子どもが自由帳に、自由にひらがなの文や、算数の問題を書き出しているのを見て、ホッとしました。
文字や、数字・計算を書く事がが好きになっていました。
あのまま続けていたら、計算は早くなっていたかもしれませんが、
うちの子では、きっと「やらされる勉強」で算数が嫌いになっていたかもしれません。
辞めてみて初めて、子どもに合う学び方の大切さを実感しました。
公文を早く辞めてよかった理由
いま思えば、「早く辞めた」のではなく、「その子に合ったタイミングで違う勉強に切り替えた」だけでした。
公文を通して「学ぶ習慣」の大切さは理解出来ました。
家での親子の時間が穏やかになりました。
やめることは、負けではありません。
むしろ、子どもの個性を見極める「勇気ある選択」だったのだと思います。
毎日の計算問題の大切さは理解していたので、自宅で計算ドリルを嫌にならない程度の量でやっています。
「公文を早く辞める=失敗」ではない

公文は素晴らしい教材です。
でも、すべての子にぴったり合うわけではありません。
大切なのは、「何を学ぶか」よりも、
「どう学ぶと、その子が伸びるか」を見極めること。
辞めたことで見えた子どもの変化は、我が家の場合は
今では、良かったと思っています。
焦らず、比べず、
世の中、特にネット上では、色々な勉強法が沢山あります。
しかし、学ぶ方の子供の年齢や成長は子供それぞれ。
AIではないので、この方法でやれば、すべての子供にとってベストとは言えないと思います。
厳しめに勉強を進めないといけない子
気持ちが弱く、優しく、揉めながら勉強を進めた方が頑張れる子
人それぞれです。
公立小学校は、勉強の進め方がみんな一緒です。
覚えが早い子は物足りない。。。
まだ、覚えが遅い子は付いていけない。。
そのズレ・歪みを、家庭でサポートしていければいいですよね。
それでは また。


